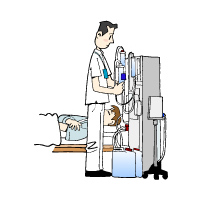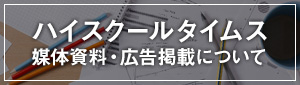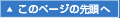東京五輪で世界にアピールするピクトグラム【国際】

【絵や記号で世界の訪問客に分かりやすく案内】
案内標識をイラストで表したピクトグラムは1964年の東京五輪で生まれました。今日では公共施設や交通機関、観光案内などあらゆる言語圏の人でも一目で理解できる「共通言語」としてなくてはならない存在となっています。2017年には外国からの訪問者により分かりやすくするため、約150種類のピクトグラムのJIS規格が改定されました。
そして今年春、2020年に開催される東京五輪のオリンピック、パラリンピックの競技案内を表すスポーツピクトグラムが新たに選定されました。日本で生まれたピクトグラムが国際コミュニケーションの有力なツールとして広がりを見せています。
 - 見るだけで誰にも分かる案内用図記号 -
- 見るだけで誰にも分かる案内用図記号 -みなさんは駅や公共施設で、「トイレ」や「エレベーター」「非常口」などを示すさまざまなマークや記号の案内表示をよく目にすると思います。言葉ではなく目で見るだけで誰にも分かるように工夫された案内用の図記号をピクトグラムといいます。
ピクトグラムは、ラテン語の「pictus」(絵)に、〜gram(書いたもの)が接続した造語です。「絵文字」や「絵単語」とも呼ばれ、何かの情報や注意を示すために表示される視覚記号(サイン)の一つです。
言葉に頼らないピクトグラムには、文字が読めなくても理解しやすく、単純化された絵柄なので遠くからでも認識しやすいメリットがあります。
- 1964年の東京五輪でピクトグラムが誕生 -
物事を簡単な絵柄で記号化して表現するピクトグラムは、主に駅や空港などの公共空間で使用されてきました。最近では一般の建物のみならず、街のインフォメーション用サインとして屋外でも広く使われています。
今私たちが目にするピクトグラムを世界に広めたのは日本でした。1964年の東京五輪で、、世界各国から訪日する外国人のために、案内表示をどうするかが問題となりました。
当時東京オリンピックのデザイン専門委員会委員長を務めた勝見勝氏が、「誰が見ても分かるマークを作ろう」と提案してピクトグラムが作成されました。
海外旅行が珍しかった当時、海外からの選手団や観戦に訪れる外国人のために、約40種類のピクトグラムが作られました。制作に携わったデザイナーたちは、「広く社会に還元すべきだ」という考えから著作権を放棄し、それによって世界的にピクトグラムが広まったといわれます。
- 20年東京五輪に向けピクトグラムのJIS規格改定 -
こうしていくつものピクトグラムが考案され、その後のオリンピックに引き継がれて各国が競技種目のピクトグラムをデザインしていくことが慣例となりました。
私たちが日常よく目にするトイレや非常口などのインフォメーション用のピクトグラムも、もともと1964年の東京オリンピックで取り入れられたピクトグラムです。
ピクトグラムは利用する人が混乱しないように規格が定められています。日本国内のみで通用する「JIS規格」と、世界中で通用する「ISO規格」があります。
近年外国からの観光客が増大しており、とくに2020年の東京五輪に向けて、外国人に分かりにくい記号の見直しが行われました。2017年にJIS規格の改定が行われ、約150種類のピクトグラムが規定されました。
JIS規格の改定と同時に、周囲に配慮や助けが必要なことを知らせるヘルプマークをはじめとした16種類のピクトグラムが新たに追加されました。
 - 今春、東京五輪、パラリンピックのピクトグラムが選定 -
- 今春、東京五輪、パラリンピックのピクトグラムが選定 -そして今年春に、2020年の東京五輪で開催されるオリンピック種目の33競技50種類の競技ピクトグラムのデザインが選定されました。12年のロンドン五輪では39種類、16年のリオデジャネイロ五輪では42種類のピクトグラムが制作されました。
競技ピクトグラムは、各競技を人型の絵文字で表す視覚記号で、会場周辺の案内板やパンフレット、チケット、国際映像にも使用され、各大会を象徴するデザインの一つとなります。
1964年の東京五輪ではなかったパラリンピック競技は、20年の東京五輪では22競技23種類が開催されますが、その競技ピクトグラムも今春選定されました。
オリンピックの競技ピクトグラムは、1964年の東京五輪で初めて登場しましたが、世界中の人々が言語を介さずに誰でも理解できる「情報伝達」手段として、オリンピック、パラリンピックを成功させるうえで、欠くことのできない存在となっています。
- 「ヘルプマークのピクトグラム」 -
ヘルプマークの人には思いやりの行動を
義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得られやすいように作成したマークを「ヘルプマーク」といいます。
2017年7月、経済産業省によるJIS規格の見直しの中で、「ヘルプマーク」のピクトグラム16種類が追加されました。ヘルプマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずり、困っている場合は声をかけるなど、思いやりのある行動を呼びかけています。