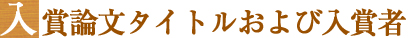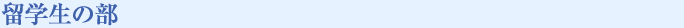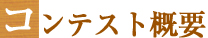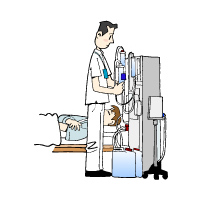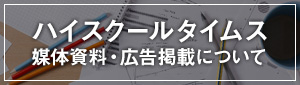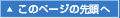「NRI学生小論文コンテスト2013」入賞者決定!!
 株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋本 正、以下「NRI」)は、「世界に向けて未来を提案しよう! あなたが考える“わくわく社会”を描いてください」をテーマとした、「NRI学生小論文コンテスト2013」の最終審査を行いました。厳正なる審査の結果、大賞3作品、優秀賞7作品、特別審査委員賞1作品を選出しました。高校生の部においては、木田夕菜さんが2年連続で大賞を受賞しました。同じ応募者が大賞を2度受賞することは、コンテスト始まって以来のことです。
株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋本 正、以下「NRI」)は、「世界に向けて未来を提案しよう! あなたが考える“わくわく社会”を描いてください」をテーマとした、「NRI学生小論文コンテスト2013」の最終審査を行いました。厳正なる審査の結果、大賞3作品、優秀賞7作品、特別審査委員賞1作品を選出しました。高校生の部においては、木田夕菜さんが2年連続で大賞を受賞しました。同じ応募者が大賞を2度受賞することは、コンテスト始まって以来のことです。このコンテストは、NRIがCSR活動の重点テーマとして掲げる「次世代の社会を担う人づくり支援」の一環として、これからの社会を担う若者に、日本や世界の未来に目を向け、考える機会を提供することを目的として2006年から毎年開催しているものです。
今回は “わくわく社会”を3部門(大学生の部、留学生の部、高校生の部)の共通テーマに設定しました。学生の皆さんには、「現状を改善する課題解決思考だけでなく、わくわく感をキーワードに、未来の社会像を構想してもらいたい。そして、その創り方や、実現のために自分たちがすべきことを、前向きに考えてもらいたい。」との想いを込めています。
2013年6月3日から9月9日までの募集期間中に、大学や日本語学校など84校、高等学校や高等専門学校など81校から、過去最多となる計1,518作品の応募がありました。
NRIグループ社員のべ123名による一次審査を経て選ばれた論文の中から、池上彰氏(ジャーナリスト・東京工業大学教授)と最相葉月氏(ノンフィクションライター)の2名を特別審査委員に迎えた最終審査会において、別記の通り入賞作品を決定しました。

若い人たちが今、「わくわく社会」や「未来」への想像力をどれだけ羽ばたかせることができるのか、大いに期待しながら審査しました。応募論文には、「現在の日本が抱えるさまざまな問題への解決策を見いだしたい」という強い意志が感じられるものが多数ありました。現実的な問題への解決策の提案を基調とする、堅実にまとめられた論文が多かったのは、やはりそれだけ今が夢を描きにくい時代であることの表れだろうと感じました。しかしながら、その中に「少しでもより良い未来を作るためには、どうしたら良いのか」と問い、真摯に突破口を開こうとする姿勢が見られたことは、非常に心強く感じられました。
「わくわく社会」という自分なりの夢と、論文としての論理的展開や具体的提案を並立させることは大変難しかったと思います。そのバランスをうまくとって書かれた作品が、今回の入賞論文となったと考えています。


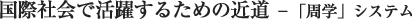
宇多 将太郎(うだ しょうたろう)さん 早稲田大学 政治経済学部 3年
日本の大学生について、一般的な留学の問題点を指摘し、1年間をかけて、世界中の大学を1ヵ月ごとに巡っていく「周学」という新しい留学システムを提案している。そのユニークな発想を高く評価した。海外数ヵ国の大学が協力し合えば、実現される可能性がある。多国籍企業がスポンサーとして参画する可能性も提示されていて、非常に斬新である。
 朝妻 美旺(あさづま みお)さん 新潟大学 教育学部 2年
朝妻 美旺(あさづま みお)さん 新潟大学 教育学部 2年
“自分の考え”をていねいに述べている点を評価した。老後への不安を期待に変えたいという思いや、高齢になっても行くところがあり、学ぶことがあることがわくわく社会の実現につながる、という主張が分かりやすい。その具体的な提案として、小学校に「高齢者学級」を作るというアイディアは、実現可能性も高く、説得力がある。

石原 純(いしはら じゅん)さん 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 博士3年
「ヒトの寿命≒健康寿命」であるピンピンコロリ(PPK)社会の実現のために、いかに先端医療技術が必要であるかということが、客観的事実も踏まえてしっかり記述されていて納得感がある。科学への信頼を得るために、科学者は自らの言葉で一般の人へ研究内容や経験を伝える努力をするべきだという考えを持ち、それを自ら実践している点も共感できる。

今井 愛美(いまい まなみ)さん 三重大学 人文学部 法律経済学科 3年
目線を高くして、難しいテーマに挑んでおり、世界の女性たちが置かれている現状に対する分析に優れている。女性教育の重要性を、多くの事例とともに論理立ててしっかりと論じていて、能動的識字教育の重要性を強く感じさせる論文になっている。
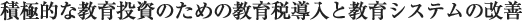
鄭 祥教(ちょん さんぎょ)さん (韓国出身)大阪大学大学院 基礎工学研究科 修士2年
教育を充実させるための特定財源として、“教育税”を創設するという具体的な提案は、検討に値するアイディアと考えられ、高く評価したい。日本の事情についても、データを多用しながら非常によく分析しており、読ませる内容になっている。日本語力の高さもさることながら、論文としてのまとまり、完成度もきわめて高い。

楊 嘉偉(やん じあうぇい)さん (中国出身)国際ことば学院日本語学校2年
留学生としての経験を踏まえた、実感のこもった文章に共感が持てる。筆者の考える“わくわく社会”のイメージを定義した点と、日本の「和」の文化、歴史的な実例なども挙げたうえで、多民族・多文化が共生する社会の姿を具体的に示している点を評価したい。

朴 管成(ぱく かんそん)さん (韓国出身)麗澤大学 外国語学部 3年
言葉に対する観察力が鋭く、「日本語と韓国語の敬語の違い」という分析視点が大変興味深い。そこから異文化を理解しようとする姿勢にも共感できる。誰もが発信できるネット社会で、あえて「聴く」ことの大切さを説いている点も新鮮であった。文章も整然として読みやすく、レベルが高い。
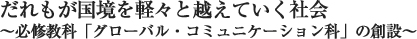
木田 夕菜(きだ ゆうな)さん 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校2年
実体験を出発点として、今のメディアの問題点を指摘し、それを全世界的な視点へと発展させている。「グローバル・コミュニケーション科」の創設、「国際教科書」、「地球的世界史」などの具体的な提案には、「その手があったか!」という思いを持った。論文としての完成度も高く、未来を見据えた高校生らしいまっすぐな姿勢に、社会を変える力と希望を感じる。

後藤 悠香(ごとう はるか)さん 大阪府立千里高等学校3年
“わくわく社会”を、「未来を想像できる社会」と明確に定義づけている点が評価できる。“わくわく社会”の実現のために、ゆとり教育を「新ゆとり教育」として再構築しようという主張に説得力がある。それを実現していくために、自ら留学を志して行動しようとする姿勢も評価したい。
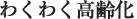
松澤 優実(まつざわ ゆうみ)さん 千葉県 市川高等学校1年
シニア問題を取り上げた論文が多く見られた中で、自身の経験や気づきに基づいて課題を絞り込み、それに対して「大学付属シルバーわくわくホーム」という具体的な提案をしている点が優れていた。客観的な情報と、自らの経験や思いをバランスよく記述していて、説得力がある。
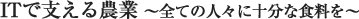
山岸 明夢(やまぎし みゆ)さん 神奈川県 湘南白百合学園高等学校2年
食物供給の偏り、飢餓、廃棄食物問題、運搬体制のゆがみといった世界レベルでの課題を提示しており、その構想の大きさを評価したい。データの扱いも非常にていねいである。ITによる生産・運搬管理という、実現可能で具体的な提案にも説得力がある。

| 応募論文総数 | 大学生の部 | 留学生の部 | 高校生の部 |
|---|---|---|---|
| 1,518 | 189 | 58 | 1,271 |
| タイトル | NRI学生小論文コンテスト2013 |
|---|---|
| 募集期間 | 2013年6月3日(月)~9月9日(月) |
| 対象 | 全国の大学院生、大学生、留学生、高校生 |
| テーマ | 世界に向けて未来を提案しよう!あなたが考える“わくわく社会”を描いてください |
| 審査のプロセス | (1)事務局による予備審査 (2)NRIグループ社員のべ123名による一次審査 (3)審査委員による二次審査(最終審査) ※すべての審査プロセスは、応募者の学校名、名前などの属性を秘匿したうえで、厳正に行っています。 |
| 審査委員 | 審査委員長 椎野孝雄(NRI理事)
特別審査委員 池上彰氏(ジャーナリスト・東京工業大学教授) 最相葉月氏(ノンフィクションライター) 審査委員 NRI役職員7名 計10名 |
| 主催 | 野村総合研究所 |
※なお、大学生の部・留学生の部では、大賞に賞金50万円、優秀賞および特別審査委員賞に25万円、佳作に5万円、また高校生の部では大賞に賞金30万円、優秀賞および特別審査委員賞に15万円、佳作に3万円が贈呈されます。
表彰式および論文発表会への取材を希望される場合は、12月18日(水)17:00までに、下記問い合わせ先までご連絡ください。
【表彰式・論文発表会への取材申し込み】
株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 清水、川越
TEL:03-6270-8100 E-mail:kouhou@nri.co.jp
【コンテストに関するお問い合わせ】
株式会社野村総合研究所「NRI学生小論文コンテスト2013」事務局 都甲、横山
TEL:03-6270-8200 E-mail:contest2013@nri.co.jp